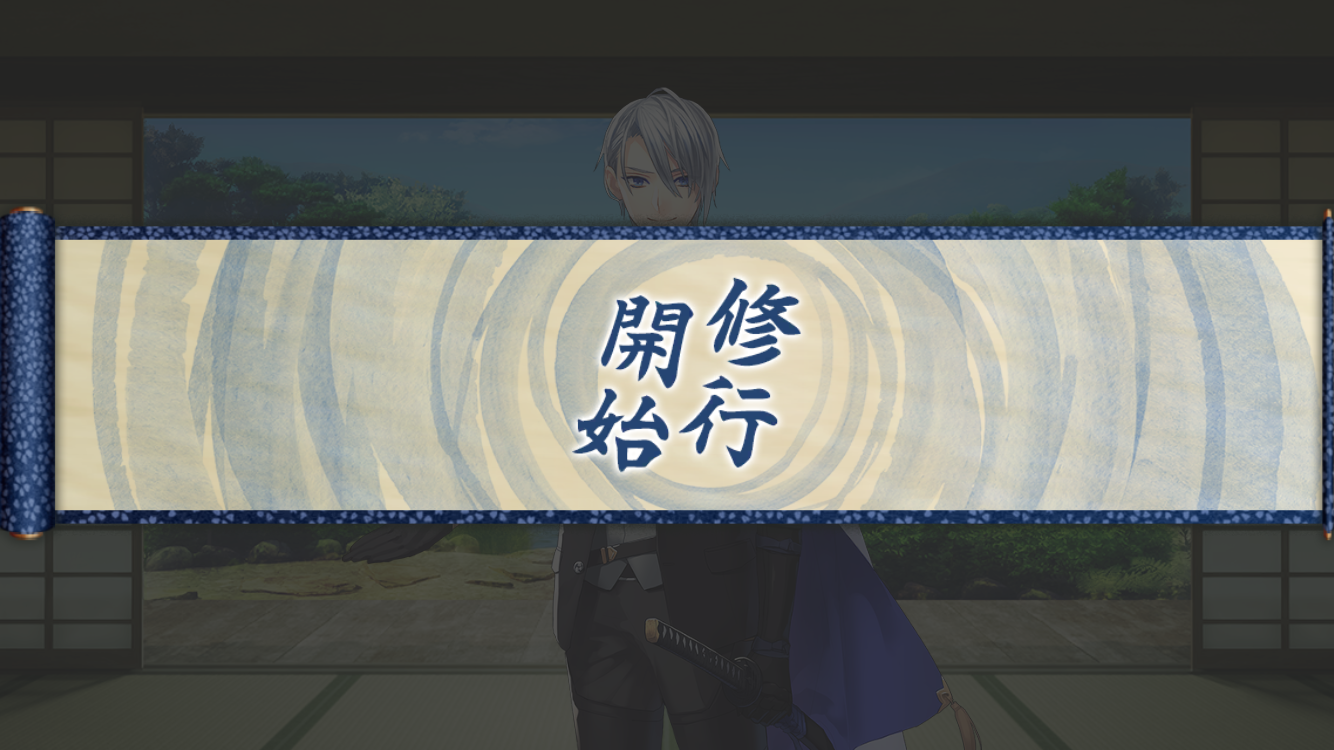No.532
審神者は検査結果を見て、ふうむと頭をひねった。
「人魚姫症候群、ねぇ……噂には聞いていたが、本当にあるものなんだな。しかも、刀剣男士に」
さて、この欠陥品をどうするか。
へし切長谷部は多少珍しくはあるものの、そこまでレアな刀というわけでもない。無難なのは、刀解して再度依代が降りるのを待つことだろう。
しかし、使えないのは声だけだ。耳や視力、四肢の異常ならともかく、声くらいであれば多少の不便があっても活用はできそうだ。
都合の悪いことに、へし切長谷部が顕現したというのは既に本丸の一部には知られてしまっている。ここでこれを刀解したとすると、顕現したことを知っている縁のある刀剣たちからの心象が悪くなる可能性がある。まだ稼働したての本丸、そうそうあることではないが、内部分裂の種になるのはできるだけ避けたい。
「……まあ、使うか。完治の可能性がないわけではない病だし」
完治の条件というのが、なんともあやふやなものゆえに、このへし切長谷部に治せるかどうかは未知数だが。それでも、完治の条件を教えておいてやれば努力くらいはするだろう。
そう思いつつ、自分に重ねて考えてみれば、努力でなんとかなる条件でもないと思うが。それは自分の性格上の問題であって、へし切長谷部ならどうにかなるかもしれないと楽観視することにする。
検査結果の紙をくるくると筒状に巻いて、審神者はへし切長谷部を待機させていた蔵の中へ足を向けた。
蔵の中に放置されていたへし切長谷部といえば。自身の置かれている現状がわからず、不安に襲われていた。
なにせ顕現した時から声が出ないのだ。明らかにこの身は欠陥品である。このまま解かされてもおかしくない。せっかくこの地に顕現したというのに、なんの役にも立てずただ解かされるだけというのはなんとも歯がゆい。
しかし、と思う頭もある。解かすのであればその場で溶鉱炉行きになっていてもおかしくない。それをわざわざひと目につかない蔵の中での待機を命じられたのは、まだ主が自分の処置を迷っているからではないのか。それならば、一筋の光明はある。今はただ、それを信じて待つしかなかった。
不安を噛み殺しながら、どれくらいの時間が過ぎたことだろう。ふいにギイ、と扉が開く。久しぶりの明かりに目を焼かれ、薄目でそちらを見る。逆光の中に、鍛刀所で見た中肉中背の男──本能的に主だと察した、人間が立っていた。
「へし切長谷部、こちらへ」
はい、主。
そう言葉にしようとして、相変わらず喉からは空気の漏れる音以外放たれない。仕方がないので一つ頷いて、その自分よりいくぶんか小さい背中を追った。
そこはいわゆる審神者の書斎、なのだろう。三方を天井まで届く本棚に覆われた小部屋の中央に、真四角の机と向かい合うように置かれた二脚の椅子がある。審神者はへし切長谷部を椅子に座るよう促すと、自身も奥側の椅子に腰掛けた。
「まず、お前のその症状について言っておこう。お前のそれは先天性声帯不全症、通称【人魚姫症候群】だ。この病名に心当たりは?」
長谷部には心当たりなどあるはずもなく、首を横に振る。
「なら、人魚姫の童話くらいは知ってるか?」
それに対しては頷く。大雑把な知識ではあるが、王子に焦がれた人魚が魔女と契約して声と引き換えに脚を得て、結ばれようと近くに寄るも恋は叶わず泡となって消える悲恋話だと記憶していた。
「それなら話が早い。要するに、今のお前は人魚姫だ。完治の方法は、想い合う誰かと両思いになること。まあ他にも手段はあるが、それは教えてやらん。思いついて実行するぶんには止めはせんが」
そんなことを淡々と言われて、長谷部は困ってしまった。今人の身を得て顕現したばかりだというのに、想う相手も想われる相手もいるはずがない。
そんな長谷部の困惑は当然理解しているのだろうが、審神者の言葉の調子は相変わらずさっぱり乾いたものだった。
「別に今じゃなくていい。過ごしていくうちに、次第に想う相手が見つかるかもしれない。それに、想う相手とは言ったが、必ずしも恋愛感情でなくてはならないわけでもないようだ。相手に何かしらの感情を抱き、その相手に何らかの感情を返される。それだけでいいらしい。ああ、失恋などしてくれるなよ。その時点でお前は泡となって消えるからな」
最後にさらっととんでもないことを言われて、長谷部はぎょっと目を剥く。誰かに心を傾けなくては治らないのに、一度の失敗でこの身は消えるのか。
「お前は声が出せない。戦では不利だろう。だが、ウチもそこまで戦力に余裕があるわけでもないんでな。戦場にも出させてもらう。他の刀より折れる可能性は高いと心得ておいてくれ。もちろん、そうならないような立ち回りをすることを期待している」
審神者の言葉に、長谷部は頷く。もとより戦の道具として呼ばれた身だ、使ってもらえるのであれば是非もない。
「……こちらからは以上だ。何かお前から質問はあるか。文字は書けるか?」
そう言って、審神者は長谷部の方に紙とシャープペンシルを差し出す。長谷部は少し悩むような素振りを見せて、すらすらとその紙に書き出した。
『主のお気遣い、痛み入ります。不束者ながら、主のお役に立てるよう努めてまいります』
審神者はその紙を一瞥して、小さくため息をつく。
「筆談は問題なさそうだな。今案内役を連れてくる。ここで待っていろ」
そう言って、審神者は部屋から出ていく。さはど時間をかけず、ふたり分の足音が戻ってきた。椅子から立ち上がり、戸に向き直る。
がらりと開いた先にいたのは、審神者と、もうひとり背の低い、白衣を纏った男だった。
「よお旦那。声が出ないたあ不便そうだな。昔の誼だ、何かあったら俺っちに頼ってくれや」
さらりとなびく黒髪、紫水晶のような透き通る瞳。どこか人形じみた顔の作りから放たれる、不釣り合いなドスのきいた声。そういえばこいつは俺の顕現の立会でもあったか、と改めて認識する。薬研藤四郎がそこにいた。
「こいつが案内役だ。立会のときにもいたし、旧知の仲でもあるし、ちょうどいいだろう。薬研藤四郎、あとは任せた」
「おう、任されたぜ、大将」
じゃあ行こうや、と踵を返す薬研の背中に、長谷部があわててついていく。後ろ髪を引かれるように、ちらりと背後を振り返ったが、審神者は興味をなくしたように無表情で戸を閉めるところだった。
「人魚姫症候群、ねぇ……噂には聞いていたが、本当にあるものなんだな。しかも、刀剣男士に」
さて、この欠陥品をどうするか。
へし切長谷部は多少珍しくはあるものの、そこまでレアな刀というわけでもない。無難なのは、刀解して再度依代が降りるのを待つことだろう。
しかし、使えないのは声だけだ。耳や視力、四肢の異常ならともかく、声くらいであれば多少の不便があっても活用はできそうだ。
都合の悪いことに、へし切長谷部が顕現したというのは既に本丸の一部には知られてしまっている。ここでこれを刀解したとすると、顕現したことを知っている縁のある刀剣たちからの心象が悪くなる可能性がある。まだ稼働したての本丸、そうそうあることではないが、内部分裂の種になるのはできるだけ避けたい。
「……まあ、使うか。完治の可能性がないわけではない病だし」
完治の条件というのが、なんともあやふやなものゆえに、このへし切長谷部に治せるかどうかは未知数だが。それでも、完治の条件を教えておいてやれば努力くらいはするだろう。
そう思いつつ、自分に重ねて考えてみれば、努力でなんとかなる条件でもないと思うが。それは自分の性格上の問題であって、へし切長谷部ならどうにかなるかもしれないと楽観視することにする。
検査結果の紙をくるくると筒状に巻いて、審神者はへし切長谷部を待機させていた蔵の中へ足を向けた。
蔵の中に放置されていたへし切長谷部といえば。自身の置かれている現状がわからず、不安に襲われていた。
なにせ顕現した時から声が出ないのだ。明らかにこの身は欠陥品である。このまま解かされてもおかしくない。せっかくこの地に顕現したというのに、なんの役にも立てずただ解かされるだけというのはなんとも歯がゆい。
しかし、と思う頭もある。解かすのであればその場で溶鉱炉行きになっていてもおかしくない。それをわざわざひと目につかない蔵の中での待機を命じられたのは、まだ主が自分の処置を迷っているからではないのか。それならば、一筋の光明はある。今はただ、それを信じて待つしかなかった。
不安を噛み殺しながら、どれくらいの時間が過ぎたことだろう。ふいにギイ、と扉が開く。久しぶりの明かりに目を焼かれ、薄目でそちらを見る。逆光の中に、鍛刀所で見た中肉中背の男──本能的に主だと察した、人間が立っていた。
「へし切長谷部、こちらへ」
はい、主。
そう言葉にしようとして、相変わらず喉からは空気の漏れる音以外放たれない。仕方がないので一つ頷いて、その自分よりいくぶんか小さい背中を追った。
そこはいわゆる審神者の書斎、なのだろう。三方を天井まで届く本棚に覆われた小部屋の中央に、真四角の机と向かい合うように置かれた二脚の椅子がある。審神者はへし切長谷部を椅子に座るよう促すと、自身も奥側の椅子に腰掛けた。
「まず、お前のその症状について言っておこう。お前のそれは先天性声帯不全症、通称【人魚姫症候群】だ。この病名に心当たりは?」
長谷部には心当たりなどあるはずもなく、首を横に振る。
「なら、人魚姫の童話くらいは知ってるか?」
それに対しては頷く。大雑把な知識ではあるが、王子に焦がれた人魚が魔女と契約して声と引き換えに脚を得て、結ばれようと近くに寄るも恋は叶わず泡となって消える悲恋話だと記憶していた。
「それなら話が早い。要するに、今のお前は人魚姫だ。完治の方法は、想い合う誰かと両思いになること。まあ他にも手段はあるが、それは教えてやらん。思いついて実行するぶんには止めはせんが」
そんなことを淡々と言われて、長谷部は困ってしまった。今人の身を得て顕現したばかりだというのに、想う相手も想われる相手もいるはずがない。
そんな長谷部の困惑は当然理解しているのだろうが、審神者の言葉の調子は相変わらずさっぱり乾いたものだった。
「別に今じゃなくていい。過ごしていくうちに、次第に想う相手が見つかるかもしれない。それに、想う相手とは言ったが、必ずしも恋愛感情でなくてはならないわけでもないようだ。相手に何かしらの感情を抱き、その相手に何らかの感情を返される。それだけでいいらしい。ああ、失恋などしてくれるなよ。その時点でお前は泡となって消えるからな」
最後にさらっととんでもないことを言われて、長谷部はぎょっと目を剥く。誰かに心を傾けなくては治らないのに、一度の失敗でこの身は消えるのか。
「お前は声が出せない。戦では不利だろう。だが、ウチもそこまで戦力に余裕があるわけでもないんでな。戦場にも出させてもらう。他の刀より折れる可能性は高いと心得ておいてくれ。もちろん、そうならないような立ち回りをすることを期待している」
審神者の言葉に、長谷部は頷く。もとより戦の道具として呼ばれた身だ、使ってもらえるのであれば是非もない。
「……こちらからは以上だ。何かお前から質問はあるか。文字は書けるか?」
そう言って、審神者は長谷部の方に紙とシャープペンシルを差し出す。長谷部は少し悩むような素振りを見せて、すらすらとその紙に書き出した。
『主のお気遣い、痛み入ります。不束者ながら、主のお役に立てるよう努めてまいります』
審神者はその紙を一瞥して、小さくため息をつく。
「筆談は問題なさそうだな。今案内役を連れてくる。ここで待っていろ」
そう言って、審神者は部屋から出ていく。さはど時間をかけず、ふたり分の足音が戻ってきた。椅子から立ち上がり、戸に向き直る。
がらりと開いた先にいたのは、審神者と、もうひとり背の低い、白衣を纏った男だった。
「よお旦那。声が出ないたあ不便そうだな。昔の誼だ、何かあったら俺っちに頼ってくれや」
さらりとなびく黒髪、紫水晶のような透き通る瞳。どこか人形じみた顔の作りから放たれる、不釣り合いなドスのきいた声。そういえばこいつは俺の顕現の立会でもあったか、と改めて認識する。薬研藤四郎がそこにいた。
「こいつが案内役だ。立会のときにもいたし、旧知の仲でもあるし、ちょうどいいだろう。薬研藤四郎、あとは任せた」
「おう、任されたぜ、大将」
じゃあ行こうや、と踵を返す薬研の背中に、長谷部があわててついていく。後ろ髪を引かれるように、ちらりと背後を振り返ったが、審神者は興味をなくしたように無表情で戸を閉めるところだった。
- ユーザ「まさ/望」の投稿だけを見る (※時系列順で見る)
- この投稿と同じカテゴリに属する投稿:
- この投稿日時に関連する投稿:
- この投稿に隣接する前後3件ずつをまとめて見る
- この投稿を再編集または削除する